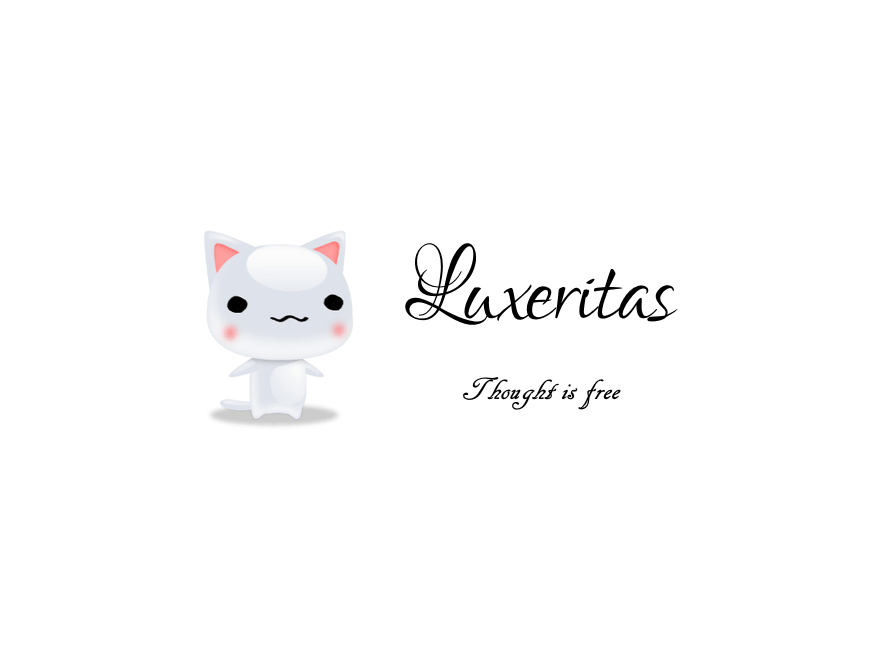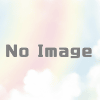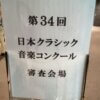コンクールではステージマナーと拍子感が大事!日本クラシック音楽コンクール予選ヴァイオリン部門を審査して感じたこと
昨年に引き続いて、日本クラシック音楽コンクール、ヴァイオリン部門の予選(8月21日(木)@すみだトリフォニー小ホール)を審査させていただきました。
担当は高校・大学・一般の部。

伸びしろの大きな演奏の数々に、演奏の前後は講評を書く手を止めて、心からの拍手を送りました!
今回、特に印象に残ったのは大きく2つのポイント。
「ステージマナー」と「拍子感」です。
いち審査員の独り言として書き留めておきます。
審査で感じたこと①:演奏前から伝わる「ステージマナー」の印象
入退場の歩き方・お辞儀で印象が変わる!
舞台に出る瞬間から演奏は始まっています。
- 楽器と弓を片手で持つ(もう片方の手を空ける)。
- 堂々と歩く。
- 美しくお辞儀をする。
これらは決して形式的なことではなく、演奏をどう受け止めてもらえるかに直結します。
審査員も人間ですから、舞台に上がったその瞬間を見て

この人はどんな演奏するのかな?ワクワク
と期待したり、

ん?大丈夫かな?
と不安に思ったりします。

ほんの数秒の立ち居振る舞いで、聴く側の心の準備は変わります。
調弦は舞台袖で落ち着いて済ませよう!
ヴァイオリンを始めとする弦楽器では、調弦も大切な要素。
本番の舞台では最終チェックだけに留められると安心です。
舞台上で大きな音で調弦するのは、正直、あまり美しくありません。

舞台袖で会場のピアノのAのピッチ(442Hzが多い)を確認して、落ち着いた場所で調弦を済ませればいいのに…と思う参加者がたくさんいました。
舞台では「日常」のちょっとした立ち振る舞いが露わに!
歩き方も、お辞儀も、調弦も、本番だけ頑張ろうと思ってもうまくいきません。

残念だけど、日頃やっていることが表れるだけだよ。
日常の姿勢の積み重ねが行動にあらわれ、「音楽と真摯に向き合っている」と感じさせる演奏につながるのだなと改めて感じました。
審査で感じたこと②:拍子感を持つことで音楽の表現が広がる
クラシック音楽は「再現芸術」。楽譜の読み込みと説得力のある演奏
今回聴いた参加者の皆さんは、表現への意欲がとてもよく伝わってきて、将来が楽しみな人がたくさんいました。
コンクール挑戦を考える(あるいは先生から薦められる)人は、最低限「音やリズムを間違えずに弾く」段階はクリアできているはずですが、
拍子感をどこまで意識できているかで、演奏の説得力に大きな差が出ていたように感じました。
クラシック音楽は「再現芸術」。
楽譜に書かれたリズムや拍子を土台にするからこそ、演奏者の個性や表現が活きてきます。
バッハ作品における舞曲と拍子感
バッハの無伴奏ソナタ・パルティータを演奏する場合に避けて通れないのが、舞曲という観点です。
昔の貴族はその音楽に合わせて踊っていたわけですから、演奏にあたって、舞曲のステップと拍子は無視できませんよね。

どんな踊りかを知って弾くと、演奏がガラッと変わりますよ。
パガニーニは確かに超絶技巧で難しいけど音楽としての魅力に溢れている
学生音コン、日本音コンの課題にもなっている、パガニーニのカプリスを弾いた方も大勢いらっしゃいました。
たしかに「悪魔に魂を売ってヴァイオリンの演奏技術を身につけた」でお馴染みのパガニーニが自分で弾くために書いた曲集ですから、並の努力では弾きこなせません。挑戦したことに対して、十分その努力を称えたい気持ちでいっぱいです。
でも、技巧的に難しいだけでなく、和声もあり拍子に則って書かれている、しっかり構成された曲集でもあります。

たしかに、ラフマニノフとかブラームスが編曲してるもんね。
音楽として魅力あふれる曲な証拠だよね。
「難しい技術できるようになった!すごいでしょ!?」だけじゃなく、「音楽」としての魅力を伝えることも忘れたくないですね。
拍子感を意識しよう
拍子感がある演奏は、聴いていて自然に体が動きますし、音楽そのものの輪郭がくっきりと浮かび上がります。
これを意識することは、将来的にどんな曲を弾くときにも大切な基礎力につながる!と感じました。

無伴奏曲は、伴奏がある曲に比べて独りよがりになりやすいですが、拍子を意識したら改善するケースが多いように感じます。
まとめ:音楽は人柄がにじみ出る!
音楽は演奏技術だけでなく、その人の人柄や日常の姿勢までが自然と表れます。
ステージマナーも、拍子感の表現も、日頃の練習や音楽との向き合い方の延長線上にあるもの。
今回聴いた演奏は、皆さん、伸びしろを感じるものばかりでした。
いつかどこかで、さらに成長した演奏を聴けるのを、心から楽しみにしています!!!
千葉県流山市のヴァイオリン・ソルフェージュ教室ホームページはこちらから。
基礎から丁寧に学び、音楽を人生の友にすることをサポートします。オンラインレッスンあり。
ソルフェージュ・ヴァイオリン・オンラインレッスンの詳細にジャンプします。

ソルフェージュの先生、ヴァイオリンの先生、時々オーケストラと室内楽。
ヴァイオリン弾きのソルフェージュ講師はわりと珍しいようです。指導経験は延べ100人以上。茨城県立水戸第三高等学校音楽科、Y. A. ミュージックアカデミー等で指導にあたる。都立芸術高校・東京藝大をヴァイオリンで卒業後、東京藝大院修士ソルフェージュ専攻を修了。
「音大受験の1科目」としてのソルフェージュではなく、実際の演奏に結び付くもの、音楽をより楽しめるものを目指しています。あらゆる楽器の生徒さんに対応していますが、得意とするのはヴァイオリンをはじめとする弦楽器。ヴァイオリンを学ぶ人に必要かつ不足しがちなことを、自身の実体験をふまえてレッスンしています。
各種レッスン受付中!詳細は下記をクリック!