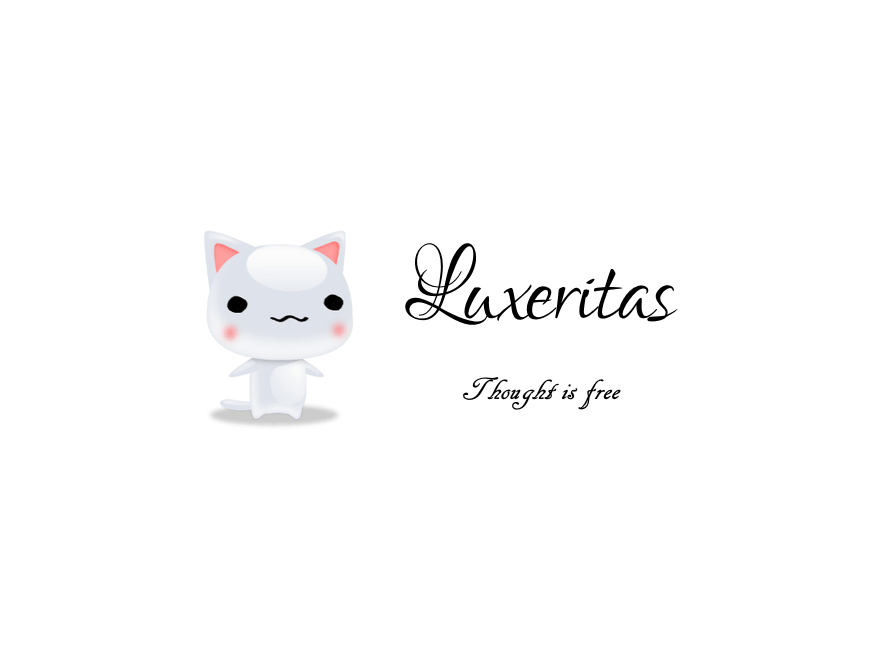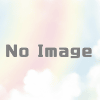アマオケのバイオリンを100倍楽しむ!レベルアップ術
今回は、アマチュアオーケストラでヴァイオリンをもっともっと楽しむためのヒントをお届けします。
楽譜通りに弾くだけで満足していませんか?

もっと上手くなりたいけど、なかなかうまく弾けない…
そんなお悩み、ありませんか?
実は、「自分のパートをちゃんと弾けるようにする」以外にも、アンサンブルが楽しくなる大切な工夫があります。
ほんの少し視点を変えるだけで、演奏の楽しさは何倍にも広がるんです!
今日ご紹介する「ちょっとした工夫」を意識するだけで、オケの時間が100倍楽しくなりますよ!
自分のパートだけ練習してもダメかもしれない理由
「まずは自分のパートをしっかり弾けるように…」もちろん大切なことです。
でも、それが最善策とは限りません。
時には他のパートとの絡みを理解したほうが、結果的に弾きやすくなることもあります。
- 他のパートが何をしているのか?
- 自分のパートとどう絡むのか?
この視点を持つだけで、演奏がグッとラクに、そして楽しくなります。
曲の全体像がわかると、世界が一気に広がります!
スコアを見よう
全体像を把握するのに最適なのは、スコア(総譜)です。
まずはスコアを絵のように眺めてみましょう!
- メロディは誰?
- 自分は支え役?対話相手?
- ハーモニーの動きは?
他のパートを聴く努力は最強のアンサンブル力につながる!
自分の演奏だけに集中していると、不思議と周りの音が聴こえなくなりがち。
でも、オーケストラやアンサンブルは 会話 に似ています。
相手の話をよく聴くことって、会話する上で大切なポイントですよね。
それは音楽も同じです。
- 相手の音に耳を傾ける
- 自分が完璧じゃなくても、まず「聴こう」とする
他の人の音を聴くと、自分の出すべき音の「居場所」が見えてきます。
完璧な人間はいない
世の中に、完璧な人なんていません(よね?)。
でも助け合えば、美しい音楽は生まれます。
みんなで支え合って、ひとつのハーモニーをつくる。
それがアマチュアオーケストラの魅力・醍醐味ですよね!

でも、みんな弾けてない所があったら、そこは本当に難しい箇所です(汗)
頑張って乗り越えましょう。
弓の端っこは、演奏効果を左右するポイント!

弓の根元や先端って、松脂をめっちゃ頑張って塗り塗りする人は多いけど、実際に使えてる人は案外少ないように感じます。
弓の根元や先端、うまく使えていますか?
オーケストラの曲には、弓の根元や先端を使うと演奏効果が爆上がりするフレーズがたくさんあります。
- 弓の根元 →物理的に重みが乗りやすく、重厚感ある音を出せる
- 弓の先端 → 木が細いので、繊細な音を出しやすい


「そういえば松脂はめっちゃ塗るけど、端っこ使ってないかも…」と思ったあなた、要チェックです!
演奏の幅がぐっと広がりますよ!
「きざみ」は見た目より奥が深い

「きざみ」ってなに?

業界用語ですね。略記法の一種です。
例をいくつかご覧ください。





でも、刻まれた形だけを頑張って練習すると、作曲家の本当の狙いを見落とします。
きざみで記譜されている時に重要なのは「音が変わるタイミング」だからです。

なんで?

音が変わる時に、響きの色合いが変わるからだよ。
つまり。
「同じ音を何回弾くか」よりも、
「音が変わるべきタイミングで音を変える」ことのほうが
何倍も大切なんです!

ほえーっ。
しつこいようですが、
「回数足りなくても然るべきタイミングで音を変える」>>>>>>>>>>>「規定回数弾く」
です!!!
きざみを正しく弾く第一歩
きざみを正しく弾く第一歩は、
原形(=刻まない形)を知ること
です。
原形を知っておけば、きざみの演奏にも自然と説得力が生まれます。

自分のパートの音が変わらなくても、他のパートの音が変わって響きが変化する時もあるよ。
やっぱり相手のパートを知ることが大切だね。
タイを外して見えてくるリズムの正体
タイ(音符同士を繋ぐ線)のあるリズムは、難しく感じている人が多く、演奏者泣かせ。


合奏で「タテ」がズレやすい場所ナンバーワン(独断と偏見)。
タイがあるリズムでタテがずれてしまうのは
「タイが無かったらどうなるか」を知らないまま、感覚で弾いてしまうから。
でも「タイ無しの形(原形)」を知っておけば、もう怖くありません!
- タイを外した形で歌う(拍をとりながら)
- タイを外した形でメトロノームに合わせて弾く
- タイ付きで歌う(必ず拍を取りながら!)
- タイ付きでメトロノームに合わせて弾く

え〜、そんなにやるの?めんどくさ〜い。
と思ったあなた。
だまされたと思って「1.タイ無しで歌う」だけでもやってみてください!
作曲家がなぜタイを使ったか、意図がわかってくるはずです。

タイが無かったら台無し。

???
スラーの裏に隠された“音楽の素”
タイとスラーが複雑に絡むフレーズ。
“うまく弾けない…”そんな経験ありませんか?
前項にある通り タイ無しで練習する ことに加えて、
スラーの無い形(原形) でも弾いてみましょう。
原形を知っておくと、スラーがどう付いても対応できます。

音楽の「骨組み」を理解してから装飾を乗せるイメージです。
まとめ:アンサンブルは「完璧」より「調和」
アマチュアオーケストラでバイオリンを100倍楽しむレベルアップ術、いかがでしたか?
- スコアを絵のように見る
- 他のパートを聴く
- 弓の端っこを使いこなす
- きざみの原形を理解する
- タイを外した形で練習する
- スラー無しでも弾けるようにする
どれも、ちょっとした視点の転換ですが、効果は絶大です。
オーケストラは、みんなで創る音楽。
自分が100%弾けなくても、耳を傾けて、気持ちを寄せていくことこそが成功の鍵です。
「完璧」を目指すよりも、「繋がり」を楽しむ。
これが、アマオケを100倍楽しむ何よりのレベルアップ術です!
千葉県流山市のヴァイオリン・ソルフェージュ教室ホームページはこちらから。
基礎から丁寧に学び、音楽を人生の友にすることをサポートします。オンラインレッスンあり。
ソルフェージュ・ヴァイオリン・オンラインレッスンの詳細にジャンプします。

ソルフェージュの先生、ヴァイオリンの先生、時々オーケストラと室内楽。
ヴァイオリン弾きのソルフェージュ講師はわりと珍しいようです。指導経験は延べ100人以上。茨城県立水戸第三高等学校音楽科、Y. A. ミュージックアカデミー等で指導にあたる。都立芸術高校・東京藝大をヴァイオリンで卒業後、東京藝大院修士ソルフェージュ専攻を修了。
「音大受験の1科目」としてのソルフェージュではなく、実際の演奏に結び付くもの、音楽をより楽しめるものを目指しています。あらゆる楽器の生徒さんに対応していますが、得意とするのはヴァイオリンをはじめとする弦楽器。ヴァイオリンを学ぶ人に必要かつ不足しがちなことを、自身の実体験をふまえてレッスンしています。
各種レッスン受付中!詳細は下記をクリック!